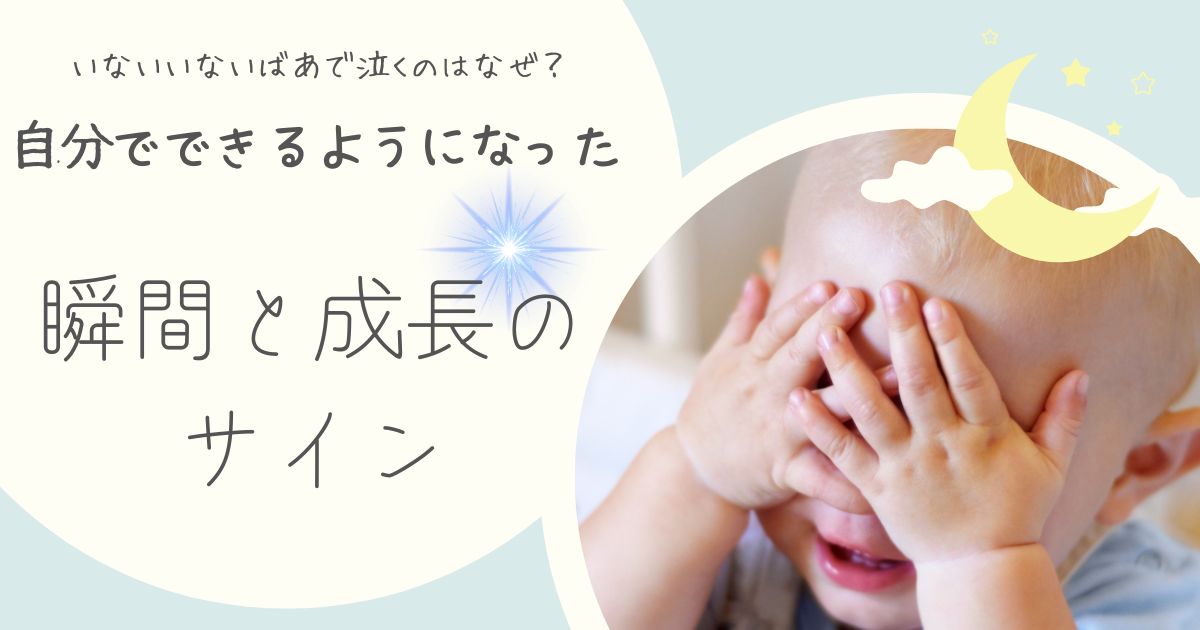「いないいないばあ」って、赤ちゃんとの初めての遊びとして定番ですよね。
うちの子が初めて「いないいないばあ」に目を向けてくれたのは、生後2ヶ月ごろ。目が見えているのか半信半疑で「これ、見えてる?」なんて妻と話しながら、そっと顔を隠しては「ばあ!」と声をかけていました。
理解はしていないだろうけど、小さな目でこちらを追ってくれる様子がうれしくて、「この子と遊べる日が来たんだな」と実感した瞬間です。
「いないいないばあ」をすると赤ちゃんが泣くこともあるとよく聞きますが、わが家では今のところ泣かれたことはありません。ただ、知らない人に話しかけられた瞬間に号泣してしまったことはあって、そんな時はベビーカーを自分に向けて、目を合わせながら「大丈夫だよ」と声をかけることで安心してもらいました。
赤ちゃんが不安を感じたときに、親の声や顔が見えることがどれだけ大切かを、あの時改めて学びました。
8ヶ月を迎えたころ、義父に
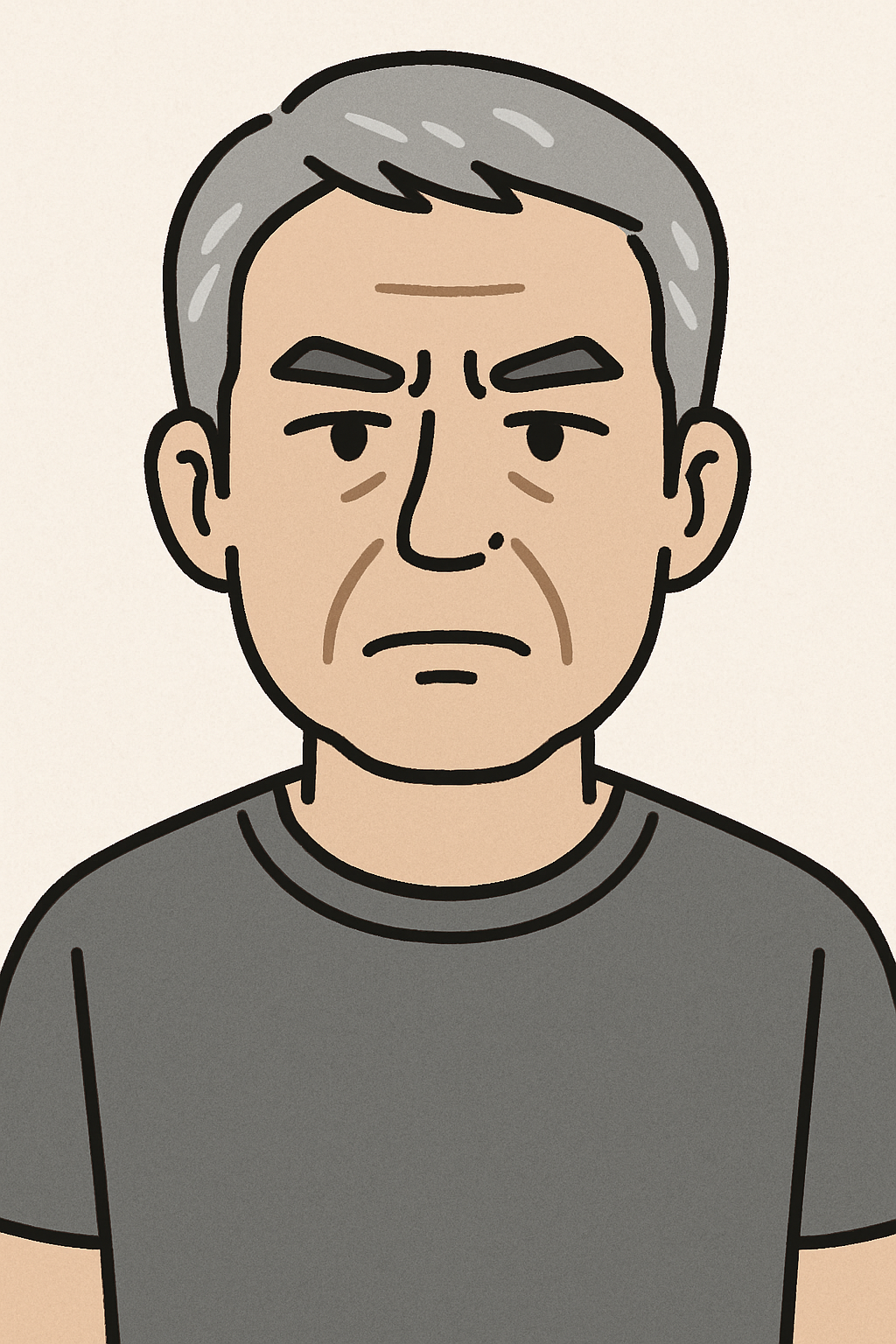
機嫌がよかったらいないいないばあを見せてくれるぞ
と言われ、「そんな大袈裟な」と思っていたら…私の予想を超える満面の笑顔で、部屋の暖簾を使って無限に「いないいないばあ!」を披露してくれたんです。あの瞬間は、ただ遊びをしているだけじゃなく、子供自身が「自分で仕掛ける」楽しさを感じているのがわかって、心から成長を感じられました。
赤ちゃんは寝返り、お座り、ずりばい、ハイハイ、つかみ食べ…と、あっという間に色んなことができるようになります。その一つひとつの姿は、今でも鮮明に思い出せるほど特別で大切な思い出です。
「いないいないばあ」も、その成長の軌跡の一つ。赤ちゃんが泣くのも笑うのも、全部が大切なサインです。
この記事では、赤ちゃんが「いないいないばあ」で泣く理由や、自分でできるようになるまでの過程、親としてできることを、わが家の体験も交えながらお伝えします。
いないいないばあで泣くのはなぜ?
赤ちゃんに「いないいないばあ」をした時、驚いて泣いてしまったという話を聞いたことがある方も多いと思います。でも実際には、赤ちゃんによって反応はさまざまです。うちの子の場合は、最初の頃はまだ表情に出ることが少なく、「ちゃんと見えてるのかな?」と不安になるほどでした。
でも成長するにつれて、「いないいないばあ」でこちらが顔を出すと、大はしゃぎしてキャッキャと声をあげて笑うようになりました。
ときにはテンションが上がりすぎて、大爆笑モードに突入することも。親としては、赤ちゃんの笑顔に釣られて、こちらまで声を出して笑ってしまうんですよね。気がつくとスマホの容量が、笑っている子どもの動画でパンパンになるほどです。

赤ちゃんが泣く理由は「驚き」と「不安」
「いないいないばあ」で赤ちゃんが泣くのは、消えたと思った顔が突然現れることに驚いたり、「いなくなった」という不安を強く感じるからと言われています。赤ちゃんは「物の永続性(物が見えなくても存在すること)」をまだ十分理解していない時期なので、顔が隠れると「本当にいなくなった」と思ってしまうのです。
泣くのも笑うのも成長過程の一部
ただ、泣くこと自体も成長の証です。「顔が見えなくなった」「また現れた」という変化を理解しようとしている証拠だからです。うちの子は幸い夜泣きはしても「いないいないばあ」で泣くことはありませんでしたが、人見知りが始まったタイミングで知らないおじさんに声をかけられたときは大号泣。すぐにベビーカーをこちらに向けて、顔を見せながら声をかけることで落ち着きを取り戻しました。
赤ちゃんは親の顔が見えるだけで安心するんだなと感じた出来事でした。
笑顔になるきっかけを作る「いないいないばあ」
「いないいないばあ」は赤ちゃんのご機嫌をとる遊びとしても優秀です。わが家では、少しぐずりそうなタイミングで「いないいないばあ!」と声をかけると、笑顔になってくれることが何度もありました。もちろん機嫌が悪すぎると、そのまま大泣きゾーンに突入することもありますが…。
赤ちゃんの笑顔は、親にとって何よりのご褒美ですよね。特別な声掛けや技術はいりません。うちも「いないいないばあ」と両手で顔を隠して開くだけ。でも、このシンプルなやり取りが、赤ちゃんにとってはとても楽しい「コミュニケーション」なんです。布や近くにあるものを使うと変化がついて、より興味を引けることもありますよ。
赤ちゃんが自分で「いないいないばあ」をできるようになる時期
赤ちゃんが「いないいないばあ」を自分でできるようになるのは、早い子で8ヶ月頃からと言われています。わが家の子も、生後8ヶ月の頃に妻の実家で初めて「セルフいないいないばあ」を披露してくれました。部屋の暖簾のようなひらひらした布を利用して、こちらの顔を見ながら「いないいない…ばあ!」と満面の笑顔。
親の私も「おおーっ!」と感動してしまい、気がつけばみんなで笑顔になっていました。
赤ちゃんが自分でできるようになるきっかけ
自分で「いないいないばあ」をやり始めるきっかけは、普段から親が楽しそうに遊んで見せること。わが家でも、私たちが「いないいないばあ!」と声をかけながら繰り返し遊ぶうちに、赤ちゃんが「これを自分もできるんだ」と気づいたようでした。
特に、暖簾(のれん)やハンカチなど、ひらひらして動きが大きい物を使うと興味を持ちやすく、赤ちゃん自身も「隠す」「現れる」という動作をやりやすいです。
セルフいないいないばあで感じた成長
初めてセルフいないいないばあを見た瞬間、「すごい!」という感動と同時に、赤ちゃん自身も「できるんだ!」という嬉しさを感じているのが表情から伝わりました。赤ちゃんはまだ人生レベル1。だからこそ、日々できることが増えていくスピードはとんでもなく早く、その成長を間近で見られる喜びは何にも代えられないなと感じました。
親子で楽しむコツ
わが家では
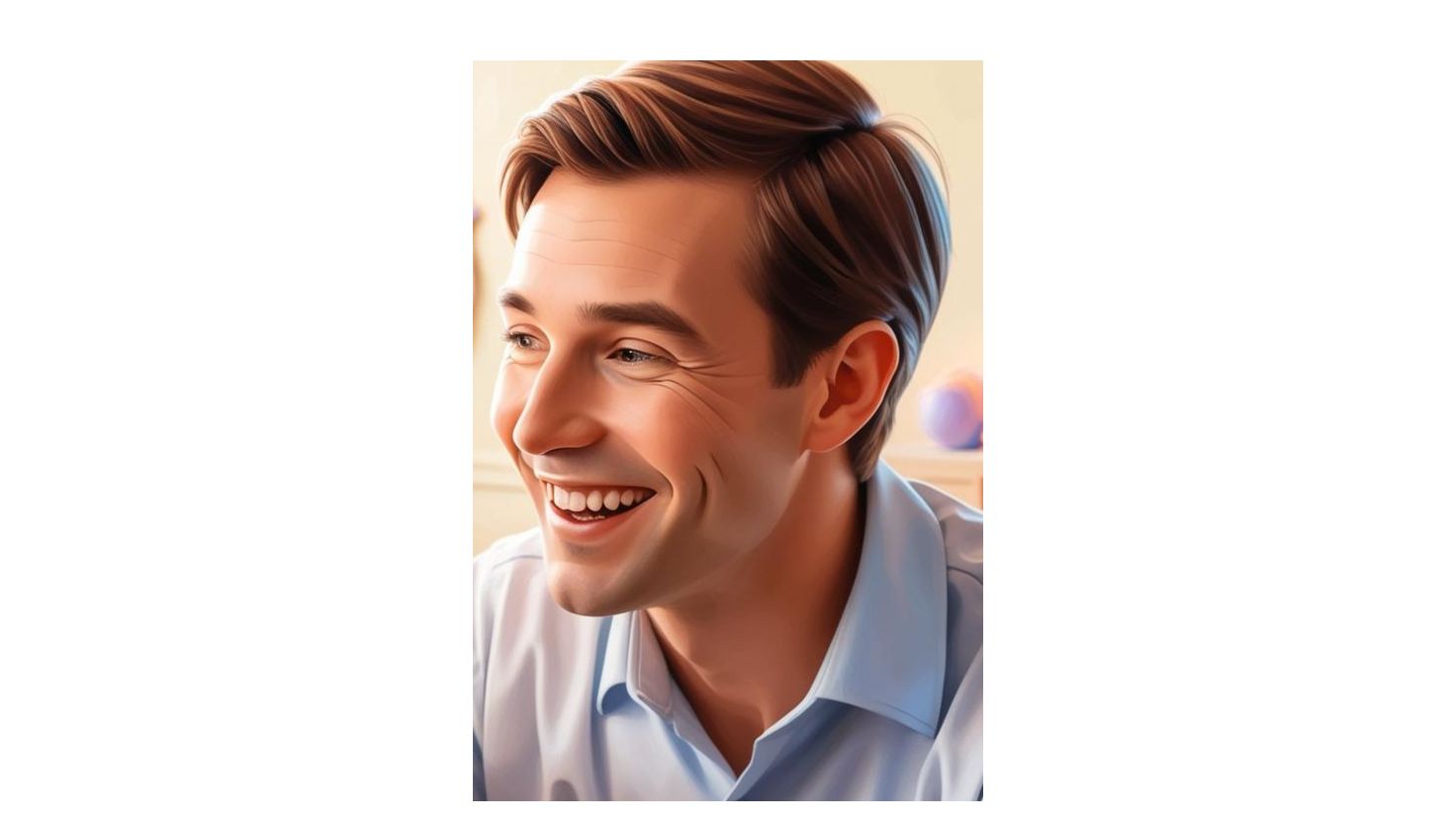
いないいないばあをやってほしいな
という時、布を手渡して「やって」と声をかけると、得意げに顔を隠して「ばあ!」と見せてくれます。際限を知らずに無限ループになるのも赤ちゃんらしさですよね。
さらに最近は、布遊びに限らずボール遊びも大好きで、こちらに向かって投げ返してくれるようになりました。もう「心のキャッチボール」が成立していて、いないいないばあを通じて育まれた「やりとり」の力が、次の遊びにも活きているんだと感じます。
自分でいないいないばあができた瞬間は成長のサイン
いないいないばあ
赤ちゃんの成長を示す大切なサイン
初期の反応
生まれて間もない頃は「笑っているように見える」だけで、自分の意思で笑っているか分からない状態
セルフいないいないばあ
自分で「いないいないばあ」ができるようになると、確実に「自分の意思」から生まれる笑顔を確認できる
感情表現の発達
笑顔が大きくなり、嬉しそうに奇声を上げるように。夜中でも「キャーッ!」と大きな声で笑う
親子の交流深化
「遊んでもらっている赤ちゃん」から「一緒に遊んでいる赤ちゃん」へと変化
✨ 成長をサポートするポイント ✨
実演・体験
親が実演し、赤ちゃんにも実際にやらせてみる
挑戦の楽しさ
うまくできなくても「挑戦する楽しさ」を感じてもらう
大げさに褒める
できたら大げさなくらい褒めてあげることを心がける
赤ちゃんが自分で「いないいないばあ」をできた時、それは小さな一歩に見えて、親にとっては大きな成長のサインです。わが家では、生まれて間もない頃は笑っている「ように見える」だけで、
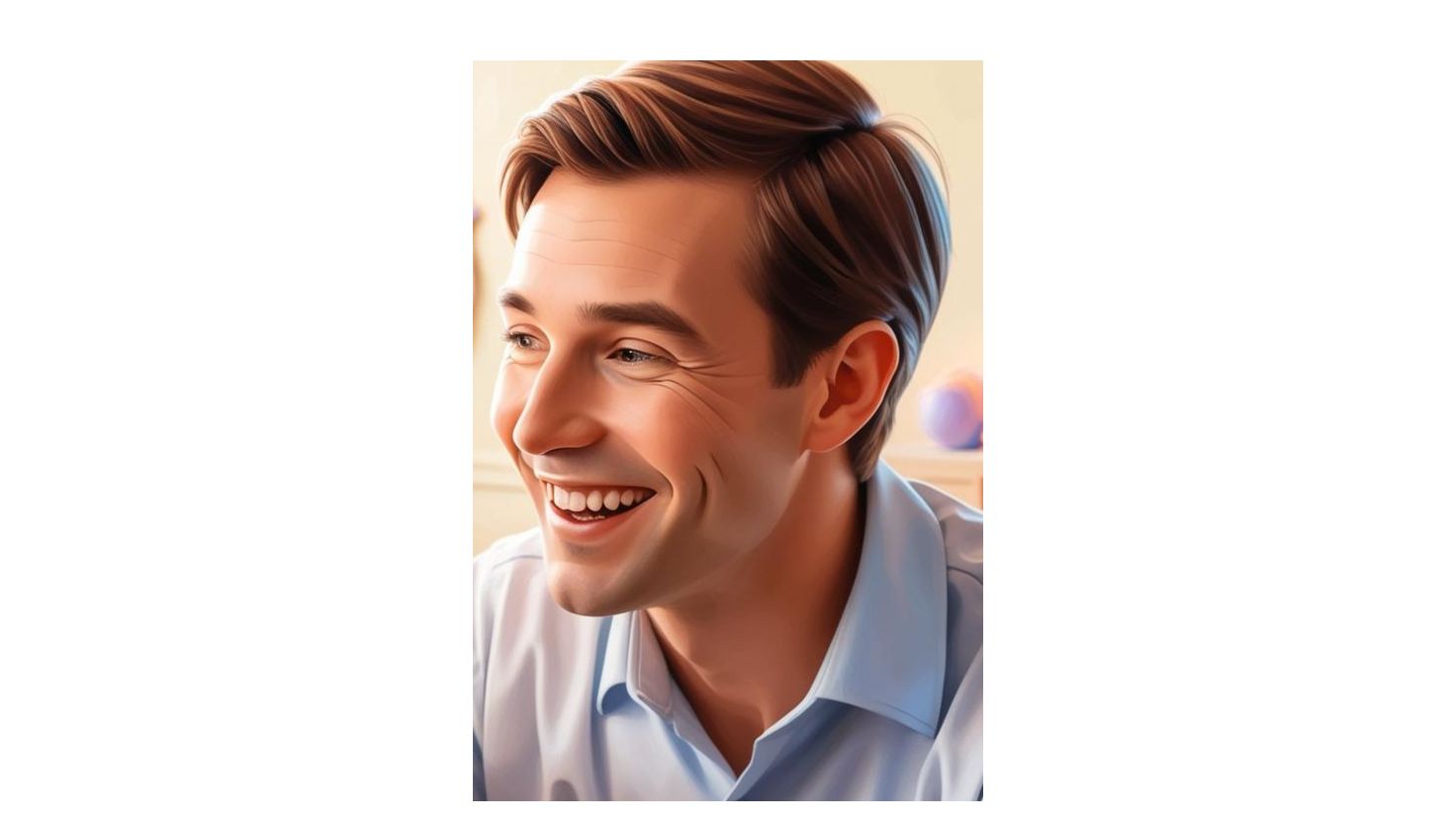
自分の意思で笑ってくれてるのかな?
とどこか寂しい気持ちになることもありました。
でも、いないいないばあを自分でできるようになってからは、赤ちゃんの笑顔が確実に「自分の意思」から生まれていると感じられるようになったんです。こちらを見ながら笑い、声を上げ、全力で「遊んでるよ!」という気持ちが伝わってくる瞬間は、親として本当に嬉しかったです。
自己認識の発達と笑顔の変化
初めてセルフいないいないばあを披露してくれた頃には、笑顔が一層大きくなり、嬉しそうに奇声を上げるようになりました。夜中でも大きな声で「キャーッ!」と笑ってしまうことも増え、
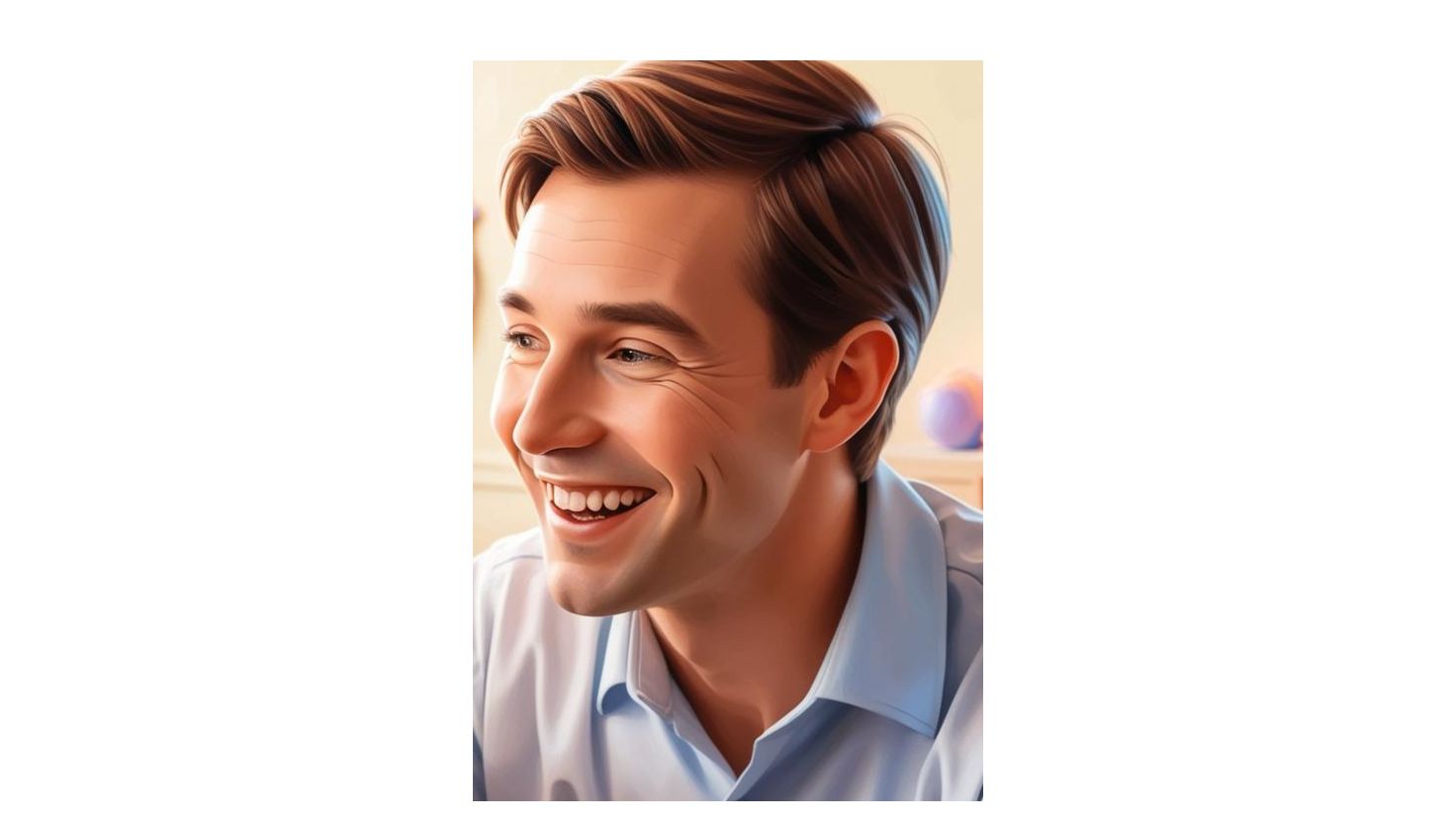
大きな声が出せるようになったのが楽しいんだな
と成長を感じる日々です。赤ちゃんが自分で考え、遊びを仕掛けてくれる姿は、意思や感情が育っている証拠だと思います。
親子で一緒に遊べるようになった喜び
「いないいないばあ」をきっかけに、親子のコミュニケーションはさらに深まりました。こちらが布を渡して「やって」と促すと、満面の笑顔で無限にばあを披露してくれる。そのうち、ボールを投げ合ったり、ハイハイで追いかけっこをしたり…「遊んでもらっている赤ちゃん」から「一緒に遊んでいる赤ちゃん」に変わってきたように思います。
新しいことへの挑戦をサポートする接し方
赤ちゃんができるようになったことは、親として大きな喜び。でもできないことの方が多いのも当然です。うちでは、何か新しいことを見せる時はまず親が実演し、赤ちゃんにも実際にやらせてみるようにしています。うまくできなくても「挑戦する楽しさ」を感じてもらえるように、できたら大げさなくらい褒めてあげることを心がけています。
まとめ|泣くのもできるのも全部成長の証!
👶 いないいないばあで見る赤ちゃんの成長まとめ
-
✅ 泣くのは成長のサイン
➔ 「物が見えなくなる不安」を感じるのも認知発達の一歩 -
✅ 笑顔は意思の現れ
➔ 自分で「いないいないばあ」をして笑うのは自己認識が育っている証拠 -
✅ 自分でできるようになる目安
➔ 多くは8ヶ月〜1歳頃にセルフいないいないばあを始める -
✅ 親子の絆を深める時間
➔ 笑顔を交わす時間が親子の信頼関係を強くする -
✅ 親が心がけたいこと
➔ 笑顔で接する、遊びを楽しむ、新しいことは見せてやらせてみる
一瞬一瞬の成長を大切に、いないいないばあで笑顔あふれる時間を楽しみましょう!
「いないいないばあ」を通して、赤ちゃんはたくさんのことを学び、できることをどんどん増やしていきます。うちの子も最初は「偶然できたのかな?」というくらいの小さな仕草でしたが、それが少しずつ確信に変わり、いつの間にか自分から「いないいないばあ!」を当たり前のように披露してくれるようになりました。
あの小さな手の中から満面の笑みが飛び出してくる瞬間は、何度見ても親として本当に嬉しくて、「この可愛さ、世界一だな」と思わずにはいられません。
「いないいないばあ」は単なる遊びではなく、赤ちゃんにとって「自分でできた!」を実感できる貴重な体験です。そして親にとっても、笑顔を交わしながらコミュニケーションが取れる大切な時間です。
わが家では、いないいないばあをしている時はいつも一緒に笑って、子どもの前ではどんな時も笑顔でいようと心がけています。
赤ちゃんが「笑顔は楽しいこと」「大好きな人が笑っていると安心できる」と感じてくれる時間を作りたいからです。
これからも、子どもが成長する中でたくさんの「できた!」を重ねていってほしい。そして将来は、人を思いやり、笑顔あふれる人生を歩んでくれることを願っています。赤ちゃんの成長はあっという間。だからこそ、いないいないばあで泣くのも、できるのも、全部が大切な成長の証だと思います。
親子で笑顔をたくさん交わしながら、この一瞬一瞬を楽しんでいけるといいですね。
▼赤ちゃんの反応に戸惑いつつも、日々の中で見つける“育児の幸せ”とは?