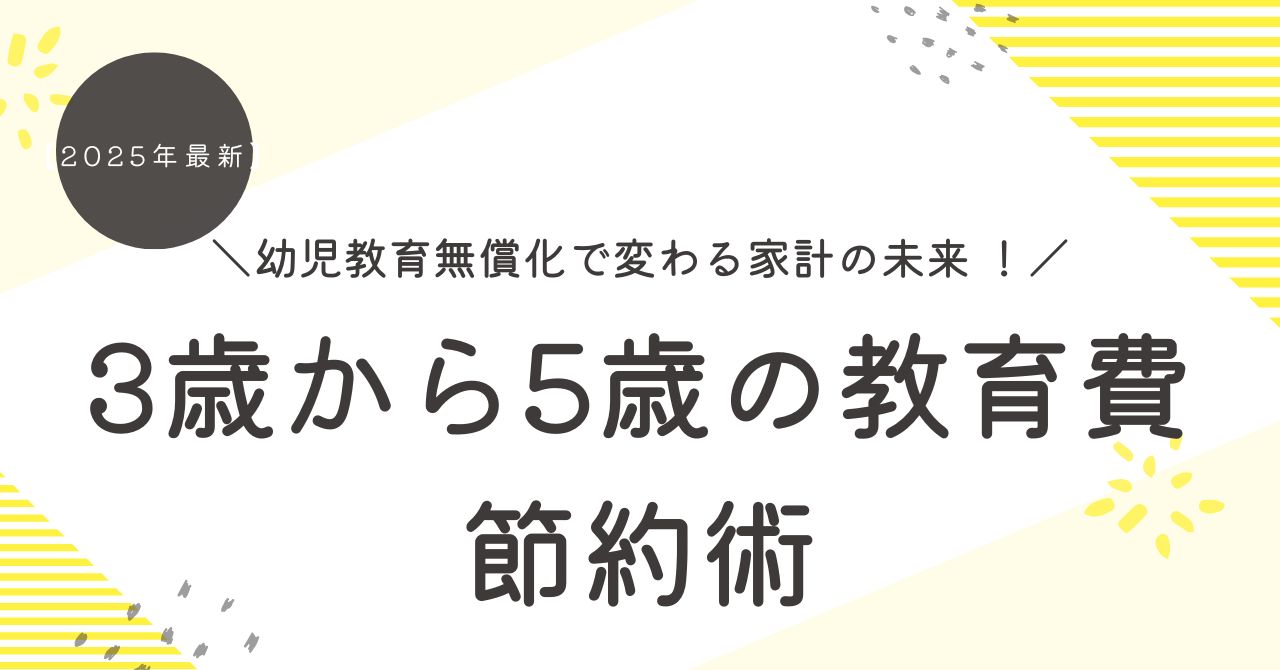子育て中のパパママの皆さん!お子さんの教育費、気になりますよね。
私も子どもを持つ親として、毎月の出費に頭を悩ませています。
でも、朗報です!2019年10月から始まった幼児教育の無償化により、多くの家庭で教育費の負担が軽くなっているんです。
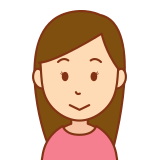
えっ、本当に?
と思われるかもしれません。
実は、この制度のおかげで、3歳から5歳のお子さんがいる約280万世帯で、1世帯平均年21万円もの負担減になっているんです。
すごいことですよね!
例えば、5歳と3歳の子どもを幼稚園に通わせている家庭では、年間で約49万円も節約できるケースもあります。
家族で旅行でも行って思い出作りできちゃいますよね。
ここで皆さんが多分思っているのは。
この制度、どうやって活用すればいいの?
どんな施設が対象なの?
そもそも、子どものお金教育はどうすればいいの?
そんな疑問にお答えするため、この記事では幼児教育無償化の仕組みや、賢い教育費の使い方、さらには子どもへのマネー教育のコツまで、わかりやすくお伝えしていきます。
家計について勉強して、明るい未来をつかみましょう。
幼児教育無償化で変わる家計の未来
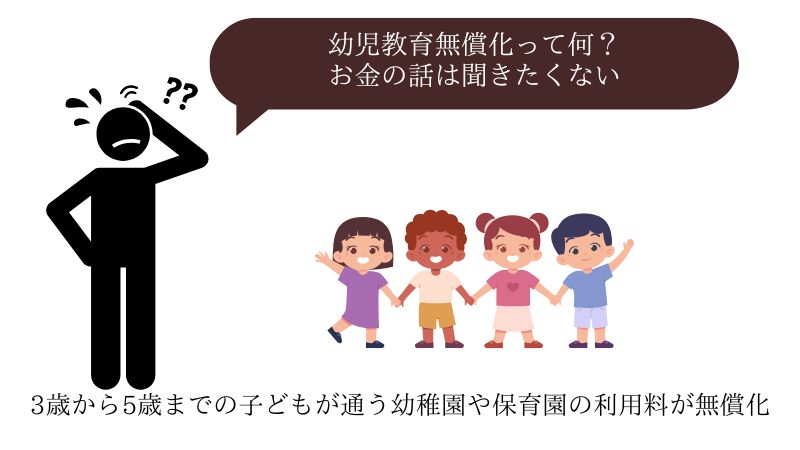
2025年からの幼児教育無償化は、子育て世代にとって大きな朗報です。
この制度により、3歳から5歳までの子どもが通う幼稚園や保育園の利用料が無償化され、家計に与える影響は計り知れません。
ここでは、無償化の仕組みや賢い教育費の使い方、子どもへのマネー教育のコツ、さらには将来の家計設計への影響について詳しく解説します。
幼児教育無償化の仕組み
幼児教育無償化は、主に3歳から5歳の子どもを対象に、幼稚園や保育園の利用料が無料になる制度です。
具体的には、月額上限が設定されており、例えば3歳から5歳の子どもは月額3.7万円までの利用料が無償になります。
この制度により、家庭の教育費負担が軽減され、他の支出に回せるお金が増えることが期待されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 主に3歳から5歳の子ども |
| 対象施設 | 幼稚園、保育園 |
| 無償化の内容 | 利用料が無料になる |
| 月額上限 | 3歳から5歳の子どもは3.7万円まで |
| 期待される効果 | – 家庭の教育費負担の軽減 – 他の支出に回せるお金の増加 |
賢い教育費の使い方
無償化によって浮いたお金は、子どもの教育や将来のために賢く使うことが重要です。
以下のポイントを参考にしてみてください。
- 貯蓄を優先する: 無償化で得たお金をそのまま使うのではなく、将来の教育資金として貯蓄することを考えましょう。例えば、子どもが大学に進学する際の学費や、習い事の費用に備えることができます。
- 教育資金の投資: NISAやジュニアNISAを活用して、教育資金を投資に回すのも一つの手です。これにより、将来的に資産を増やすことが可能になります。ジュニアNISAは、子ども名義での投資ができ、非課税で運用できるため、教育資金の準備に適しています。
子どもへのマネー教育のコツ
子どもにお金の大切さを教えることも、無償化制度を活用する上で重要です。
以下の方法で、楽しくマネー教育を行いましょう。
- お買い物ごっこ: 子どもと一緒にお買い物ごっこをすることで、実際にお金を使う感覚を学ばせることができます。遊びながらお金の使い方を理解させることができるため、効果的です。
- 日常会話にお金の話を取り入れる: 家族の会話の中にお金の話題を取り入れることで、子どもが自然にお金について考える機会を増やします。例えば、なぜその商品を買うのか、どのようにお金を管理するのかを話し合うことが大切です。
将来の家計設計への影響
無償化制度は、将来的な家計設計にも大きな影響を与えます。
教育費の負担が軽減されることで、他の生活費や貯蓄に回せるお金が増え、家計全体の安定性が向上します。
また、子どもが成長するにつれて、教育資金を計画的に準備することができるため、安心して子育てを続けることができるでしょう。
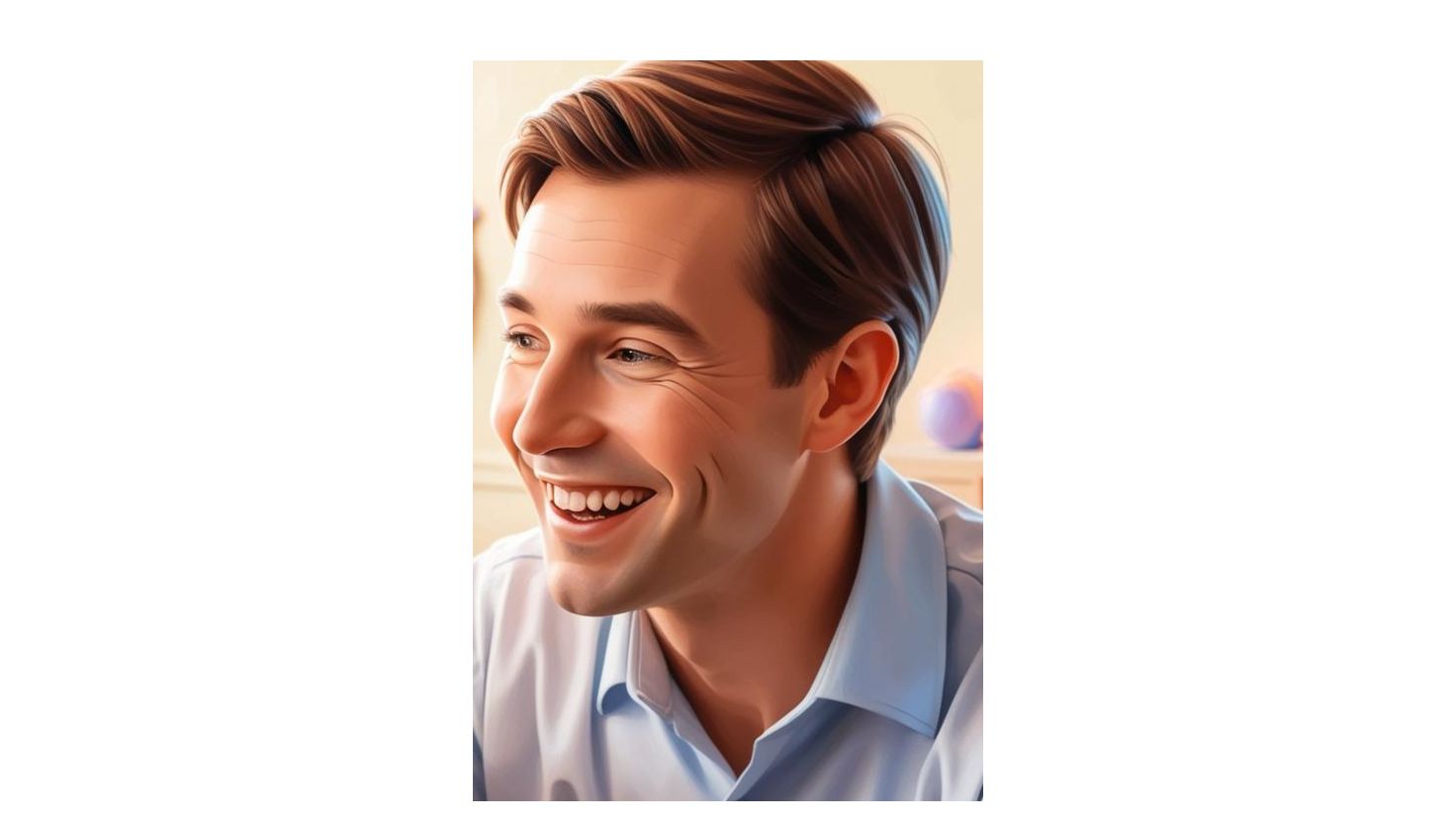
2025年からの幼児教育無償化は、家計にとって大きな助けとなります。
この制度を上手に活用し、賢い教育費の使い方や子どもへのマネー教育を行うことで、将来の家計設計にも良い影響を与えることができます。
ぜひ、無償化制度を活用して、子供の未来の選択肢を増やしてあげましょう。
幼児教育・保育の無償化!子育てを支える新しい制度の理解
皆さんが気になる「幼児教育・保育の無償化」って何なのかな?という疑問。
簡単に言うと、子どもたちが幼稚園や保育園に通うときのお金を、国が助けてくれる仕組みなんです。
やったーと思っているかもしれませんが注意!「無償化」って聞くと
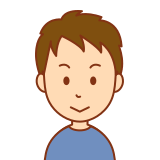
全部タダになるの?
って思うかもしれないけど、実はそうじゃないんです。
家族のお金持ち具合や、通っている園によっては、お金がかかることもあるんです。
そして、この制度を使えるかどうかは、毎年4月1日の子どもの年齢で決まるんです。
つまり、4月1日に3歳以上の子どもたちが主な対象になるってわけですね。
ただその限りではない!0歳から2歳の子どもたちも、家族のお金事情によっては対象になることもあるんです。
この制度のおかげで、たくさんの家族が子育ての負担を減らせるようになりました。
でも、完璧な制度ではないから、自分の家族に当てはまるかどうか、よく確認してみるのがいいかもしれないですね。
子育ては大変だけど、こういう制度を上手に使えば、もっと楽しく子育てができるかもしれないですよ。
こいった制度を上手く活用して子供の未来を豊かなものにしましょう!
幼児教育・保育の無償化制度による子育て支援の変化
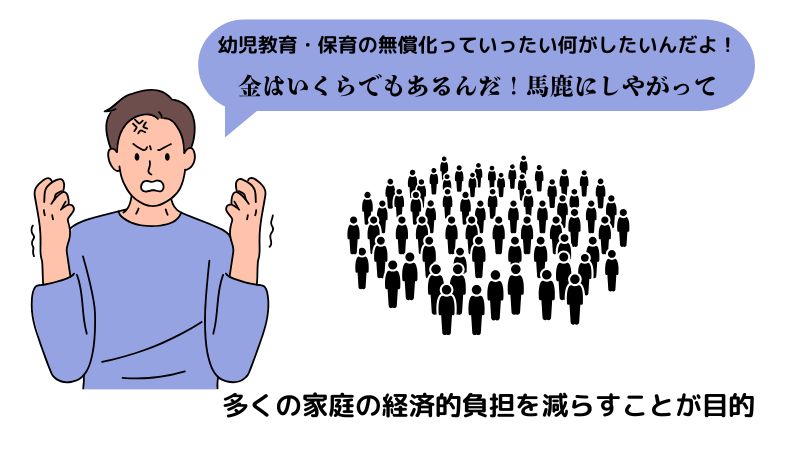
幼稚園や保育園に通う子どもたちの費用が、2019年10月から大きく変わりました!これは「幼児教育・保育の無償化」と呼ばれる制度で、多くの家庭の経済的負担を減らすことを目的としています。
こういうのって何処で習うんでしょうね。
3歳から5歳までの子どもたち
3歳から5歳までのすべての子どもたちが、幼稚園や保育園、認定こども園などの基本的な利用料が無料になりました。
これは、子どもが満3歳になった後の4月1日から小学校に入学するまでの3年間が対象です。
ただし、幼稚園に通う場合は少し特別で、入園できる時期に合わせて満3歳から無料になります。
幼稚園によっては、月額2.57万円までが無料となる場合もあります。
ちなみに制服代や通園バス代、給食の食材代などは実費として支払う必要があります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象年齢 | 3歳から5歳まで |
| 対象施設 | 幼稚園、保育園、認定こども園など |
| 無料期間 | 満3歳になった後の4月1日から小学校入学まで(3年間) |
| 幼稚園の特例 | 満3歳から無料(入園できる時期に合わせて) |
| 幼稚園の無料上限額 | 月額2.57万円まで(園によって異なる) |
| 実費負担項目 | 制服代、通園バス代、給食の食材代など |
0歳から2歳までの子どもたち
0歳から2歳までの子どもたちの場合、住民税非課税世帯のみが無料になります。
ただし、2人以上子どもがいる家庭では、上の子から順に数えて、2番目の子は半額、3番目以降の子は無料になるという仕組みもあります。
住民税非課税世帯になるには
・所得基準: 世帯全員の前年の合計所得が一定の基準を下回る必要があります。例えば、単身者の場合、前年中の合計所得が45万円以下であれば非課税となります。
・特定の状況: 生活保護を受けている人や、障害者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親で前年の合計所得が135万円以下の場合も非課税の対象となります。
対象となる施設

無料になる施設は、幼稚園、保育所、認定こども園だけでなく、地域型保育や企業主導型保育事業も含まれます。
地域型保育とか企業主導型保育事業ってなんだよって思いますよね。
地域型保育事業は、主に0歳から2歳の子どもを対象とした小規模な保育サービス。
企業主導型保育事業は、企業が自社の従業員のために設置する保育施設。
と覚えておいてください、
注意点
- 通園バスの費用やお弁当代、行事の費用などは、これまでどおり保護者が払う必要があります。
- ただし、年収360万円未満の家庭や、3人目以降の子どもの場合は、おかずやおやつなどの費用(副食費)が免除されます。
- 幼稚園の種類によっては、無料にするための手続きが必要な場合があります。詳しくは、住んでいる市区町村の役所に確認してみましょう。
この制度により、多くの家庭で子育ての経済的な負担が軽くなりました。
でも、細かい条件もあるので、自分の家庭がどのような支援を受けられるのか、しっかり確認することが大切です。
あてはまる人は少しでも子育ての負担を減らして、素敵な思い出作りをしてください!
預かり保育のメリットと利用方法
預かり保育って何?
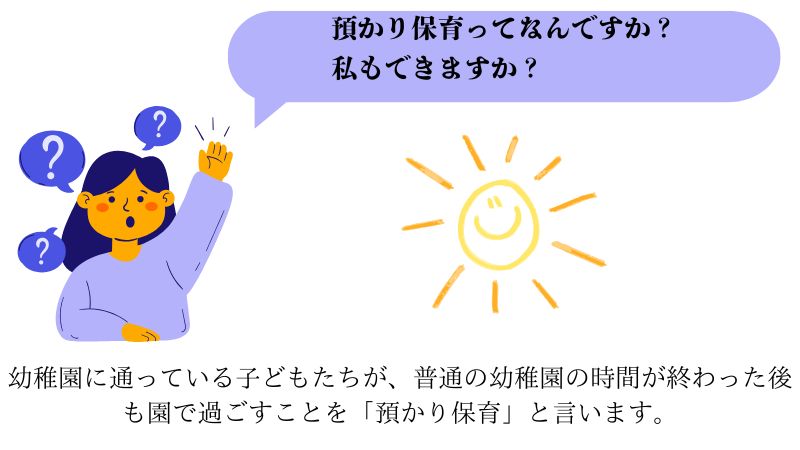
幼稚園に通っている子どもたちが、普通の幼稚園の時間が終わった後も園で過ごすことを「預かり保育」と言います。
働くお父さんやお母さんにとって、とても助かるサービスですよね。
預かり保育の費用は?
預かり保育にもお金はかかりますが、こちらも国が応援してくれています。
- 3歳から5歳までの子どもたち:1ヶ月に最大11,300円まで無料
- どのくらい使ったかによって、実際に無料になる金額が決まります
どうすれば無料になるの?
ここが大事です!無料にするには「保育の必要性の認定」という手続きが必要です。
簡単に言うと
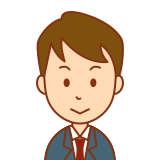
この家族は預かり保育が必要だね
と市役所に認めてもらうことです。
仕事をしているとか、病気のため家で子どもの面倒を見るのが難しいとか、そういう理由が必要になります。
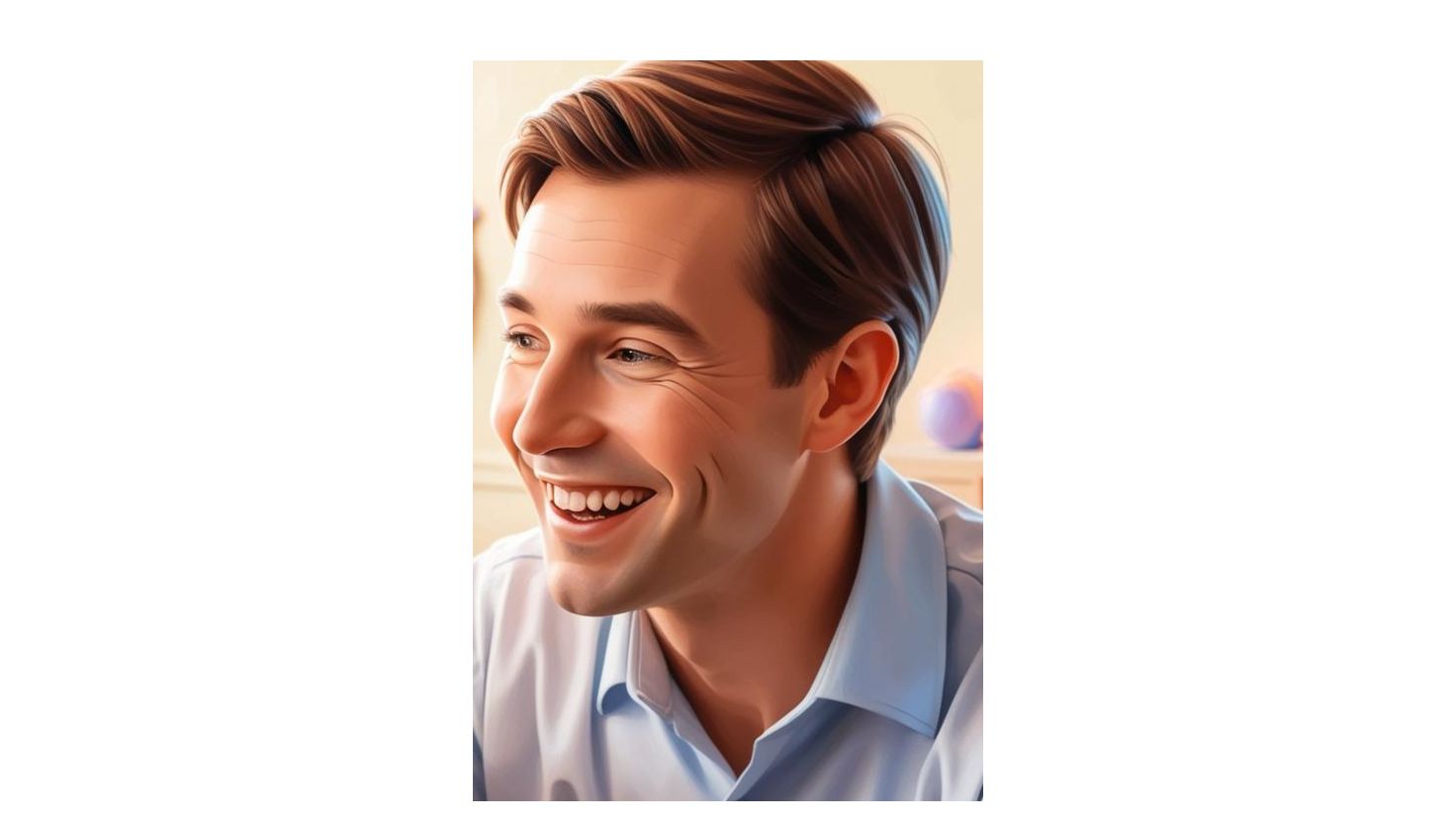
子育ては楽しいけれど、お金のことを考えると不安になりますよね。
でも、こうやっていろいろな支援があることを知ると、少し安心できませんか?
わからないことがあったら、住んでいる地域の市役所や幼稚園に聞いてみてください。
きっと丁寧に教えてくれるはずです。
国の力を借りてお金の問題も乗り越えましょう。万歳!
認可外保育施設の魅力と利用方法
認可外保育施設って、ちょっと変わった保育園なんです。
普通の保育園とは違って、国からのお墨付きはないけど、子どもたちを預かってくれる場所なんです。
しかし、心配しないでください。
ちゃんと法律で認められているんですよ。
認可外保育施設には、いろんな種類があります。
普通の小さな保育園みたいなものから、会社の中にある保育所、赤ちゃんの家に来てくれるベビーシッターさんまで。
他にも、急に子どもを預けたいときに使える一時預かりや、子どもが病気のときに預かってくれる病児保育もあります。
助かるポイントは、これらの施設を使うと、お金の補助が受けられることです。
3歳から5歳の子どもなら、月に3万7千円まで無料になります。
0歳から2歳の赤ちゃんも、住民税非課税世帯の場合は、月に4万2千円まで無料になるんです。
でも、ただ預けるだけじゃダメなんです。
市役所に
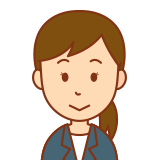
うちの子、保育が必要なんです
って申請しないといけません。
そして、親が仕事をしているなど、ちゃんとした理由が必要です。
大事なのは、どの認可外保育施設でもOKというわけじゃないってこと。
都道府県に届け出て、国が決めた基準を満たしている施設じゃないとダメなんです。
認可外保育施設は、普通の保育園よりも自由に運営できるので、独自のサービスを提供できるのが魅力です。
でも、その分、親御さんがしっかり確認する必要があります。
施設を見学したり、保育の内容を聞いたりして、自分の子どもに合っているか確かめましょう。
育児は大変ですが、こういった施設を上手に使えば、子育ての強い味方になりますよ。
認可外保育施設、実は結構便利で、ちゃんと法律で認められた子育てのサポート役なんです。
障害のあるお子さんのための無料発達支援サービスのご案内
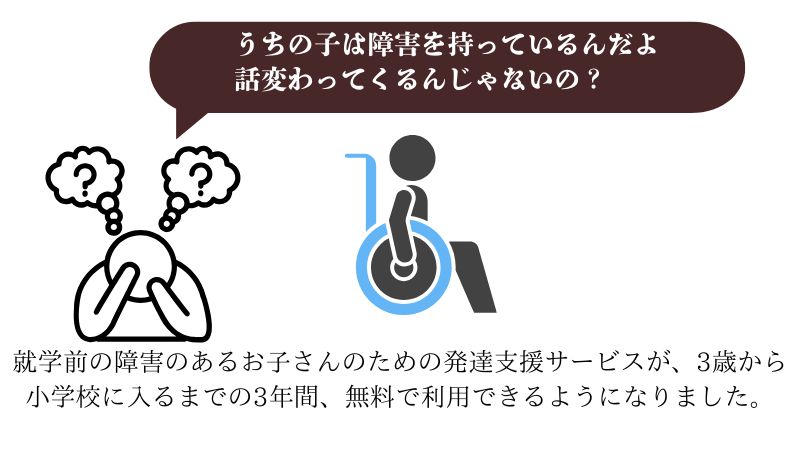
就学前の障害のあるお子さんのための発達支援サービスが、3歳から小学校に入るまでの3年間、無料で利用できるようになりました。
これは、子育て中のみなさんにとってうれしいニュースですね!
対象となるのは、児童発達支援や医療型児童発達支援、お家に先生が来てくれる居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、そして障害児入所施設などです。
これらのサービスを使うと、お子さんの成長をしっかりサポートしてくれます。
無料になる期間は、お子さんが3歳になった後の最初の4月1日から、小学校に入学するまでの3年間です。
例えば、4月2日生まれのお子さんなら、4歳になった年の4月から小学校入学までということですね。
うれしいことに、幼稚園や保育所、認定こども園などと一緒に利用しても、両方とも無料になります。これで、お子さんに合わせたさまざまな支援を受けられますね。
ただし、注意してほしいのは、利用料以外の費用は自己負担になることです。
例えば、医療費や食事の材料費などは、これまでどおり払う必要があります。
これらの費用は、障害のないお子さんと同じように扱われます。
新しく手続きをする必要はありませんが、利用している施設に、お子さんの年齢を伝えて、無料の対象になることを確認しておくといいでしょう。
この制度のおかげで、障害のあるお子さんも、みんなと同じように成長のチャンスを得られるようになりました。
子育ては大変ですが、こういった支援を上手に使って、お子さんの笑顔を増やしていけたらいいですね!
保育料無償化の対象施設を簡単に探す方法!
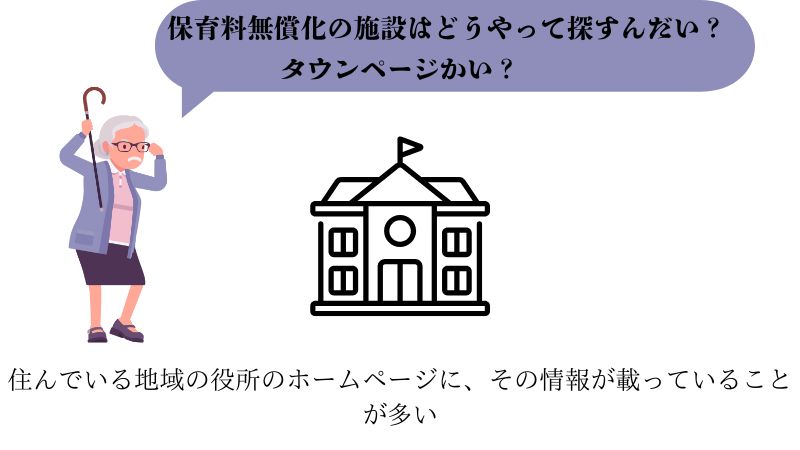
保育料無償化の対象となる園を探すのは、実はとても簡単なんです!みなさんが住んでいる地域の役所のホームページに、その情報が載っていることが多いんですよ。
でも、「自治体」って聞いてピンとこない人もいるかもしれませんね。
自治体というのは、みなさんが住んでいる市や町、村のことを指します。
例えば、東京都新宿区に住んでいる人なら、新宿区が自治体になります。
さて、その自治体のホームページを見つけたら、次は何をすればいいでしょうか?
そう、検索です!ホームページの上の方にある検索窓に、「保育料無償化 対象施設」と入力してみてください。
きっと、あなたの地域で無償化の対象となる保育園や幼稚園のリストが出てくるはずです。
もし検索してもすぐに見つからない場合は、諦めないでくださいね。
役所の子育て支援課や保育課に電話をして聞いてみるのも良い方法です。
親切に教えてくれるはずですよ。
子育ては初めてのことばかりで大変かもしれません。
でも、こういった情報をしっかり集めることで、少しずつ子育てのプロになっていけるんです。
一緒に頑張りましょう!
幼児教育・保育の無償化!3~5歳の開始年齢とその違いについて
先ほどの説明に加えて、もう少し詳しく説明しますね。
3~5歳までの幼児教育・保育の無償化について、開始年齢が施設によって異なるんです。
これは少し複雑なので、表にしてみました。
| 対象 | 無償化の開始年齢 |
|---|---|
| 保育園・認定こども園(保育園部分)に入園している方 | 3歳の誕生日を迎えた後の4月以降 |
| 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に入園している方 | 3歳の誕生日以降 |
つまり、保育園や認定こども園の保育園部分を利用している子どもさんは、3歳の誕生日を迎えてからすぐには無償化されません。
次の4月を待つ必要があります。
一方、幼稚園や認定こども園の幼稚園部分を利用している子どもさんは、3歳の誕生日からすぐに無償化の対象になります。
これって、ちょっと不公平に感じますよね?
実は、この違いには理由があるんです。
幼稚園は昔から3歳になったらすぐに入園できる仕組みだったので、その慣習を尊重しているんです。
でも、認定こども園ならちょっとしたワザがあります。
認定こども園は、保育園と幼稚園の良いところを合わせた施設なので、3歳の誕生日が来たら、保育園枠から幼稚園枠に変更できるんです。
そうすれば、環境を変えずに早く無償化の恩恵を受けられます。
育児は大変ですが、こういった制度をうまく活用すれば、少しでも家計の負担を減らせるかもしれません。
ぜひ、お住まいの地域の役所に相談してみてくださいね。
混んでいるかもしれませんが、その分いいアドバイスを貰いましょう。
無償化の真実。幼稚園・保育園にかかる費用を知ろう!

ママ・パパ、お子さまの幼稚園や保育園、楽しみですね!ここで、おさらいです!
無償化って聞いたけど、全部タダになるわけじゃないんです。
ビックリしちゃうかもしれませんが、お財布の準備はまだ必要なんですよ。
じゃあ、どんなお金が必要なの?
簡単に説明しますね!
保育園や認定こども園(保育園部分)の場合
- お弁当を作らなくていいのは嬉しいけど、おかずやおやつ代は支払いが必要です。でも、家族の状況やお給料によっては、これが無料になることもあるんですよ。
- バス代や遠足代、絵本代なんかも別途かかっちゃいます。
- 仕事が遅くなって延長保育を使うときも、追加のお金がかかります。
幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)の場合
- ここでも、バス代や遠足代は支払いが必要。
- 給食代も別途かかります。
- PTA会費も忘れずに!これも払わなきゃいけないんです。
無償化って言われても、実はこんなにいろいろお金がかかるんですね。
びっくりしちゃいました?
覚えておいてよかったですね!事前に知っておけば、しっかり準備できますよね。
子育ては楽しいけど、お金のことも大切。
これを知っておけば、慌てずに済みますよ。
子供が楽しく園で過ごせるといいですね!
幼児教育・保育の無償化手続きガイド
幼児教育・保育の無償化を利用するための手続きは、利用する施設によって異なります。
子ども・子育て支援新制度の対象施設(幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育)を利用する場合は、特別な手続きは必要ありません。
通常の保育認定を受けて施設と契約すれば、自動的に無償化の対象となります。
一方、認可外保育施設等(認可外保育所、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター、病児保育事業)を利用する場合は、以下の手続きが必要です
- お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける。
- 利用料を一旦自己負担で支払う。
- 施設から領収証などの支払い証明を受け取る。
- 市町村に必要書類を提出して費用を請求する(償還払い)。
請求の締切や方法は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
そんな施設あるの?と思いますよね。
旧制度の幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園)を利用する場合は、別途申請が必要で。
申請書類は幼稚園から配布され、幼稚園を通じて市町村に提出します。
無償化の対象となる金額や年齢は施設によって異なりますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
早生まれの子どもの幼児教育・保育無償化の違いを理解しよう!

早生まれの子どもの幼児教育・保育無償化について、ちょっと複雑なので、分かりやすく説明しますね。
まず、保育所と幼稚園で違いがあるんです。
ここまでOKですか?
保育所の場合
保育所に通う子どもたちは、みんな平等に3年間無償になります。
3歳の誕生日の次の4月1日から小学校に入るまでの3年間、お金がかからないんです。
だから、早生まれの子も遅生まれの子も、同じ3年間タダで通えるんですよ。
| 生まれ月 | 無償化開始 | 無償化期間 | 小学校入学 |
|---|---|---|---|
| 4月~3月 | 3歳の誕生日の次の4月1日 | 3年間 | 6歳の4月 |
幼稚園の場合
ここがちょっとトリッキー。
幼稚園は満3歳になったその日から無償化が始まります。
つまり、誕生日が来たらすぐにタダになるんです。
でも、ここで面白いことが起きるんです。
4月生まれの子と3月生まれの子を比べてみましょう。
- 4月生まれの子:3歳の誕生日から小学校入学まで、丸々3年間無償
- 3月生まれの子:3歳の誕生日から小学校入学まで、約2年1ヶ月間無償
なんと、同じクラスなのに無償期間に11ヶ月もの差が出ちゃうんです。
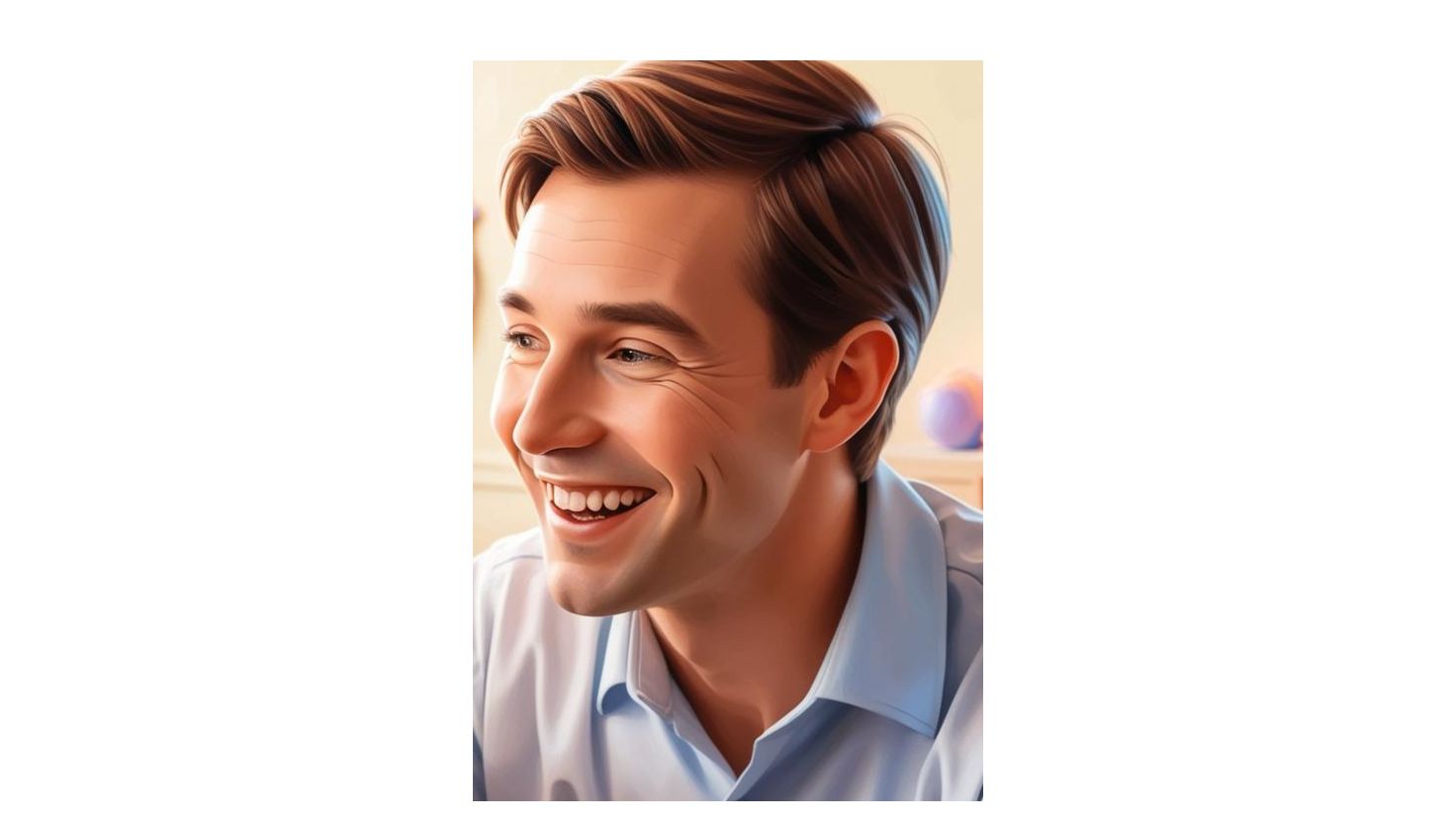
結局のところ、早生まれの子どもの親御さんは、この違いをよく理解しておく必要があります。
保育所なら問題ないけど、幼稚園を選ぶなら無償化の期間が短くなる可能性があるってことですね。
でも、無償化の期間だけで施設を選ぶのではなく、お子さんに合った環境を選ぶことが一番大切です。
無償化は確かにありがたいけど、それ以上に子どもの成長と幸せが大切ですからね。
育児は本当に奥が深いです。
こういった制度があるだけありがたいと思って活用しましょう!
まとめ
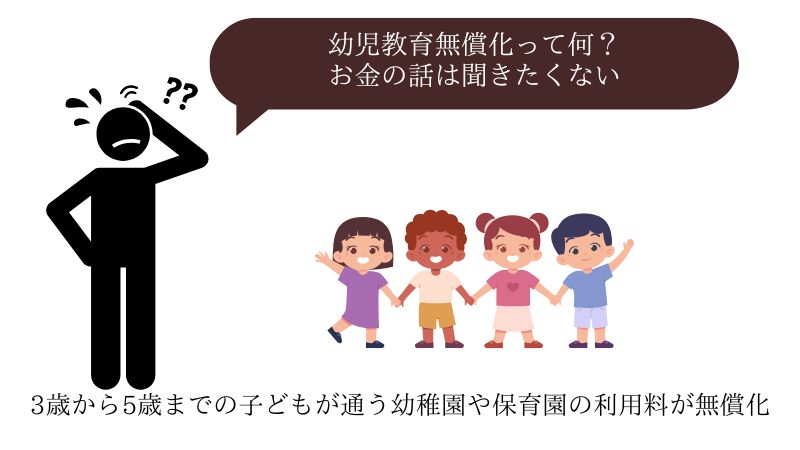
2025年から始まる幼児教育無償化は、子育て中のみなさんにとってうれしいニュースです。
3歳から5歳までの子どもたちが通う幼稚園や保育園のお金が無料になるんです。
これで家計の負担がグッと減りそうですね。
もっと子供が喜ぶ事にもお金が使えますね。
無償化ってどんな仕組み?
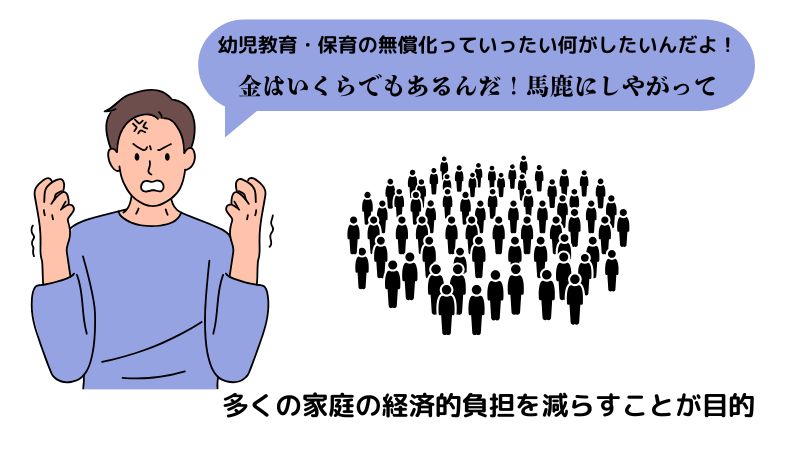
簡単に言うと、幼稚園や保育園に払うお金が無料になるんです。
3歳から5歳の子どもなら、月に3.7万円まで無料になります。
これで、今まで教育にかけていたお金を他のことに使えるようになりますよ。
素敵な思い出を作りましょう。
お金の賢い使い方
旅行やプレゼントも素敵ですが、無料になったお金、どう使えばいいの?
ここがポイントです
- 貯金しよう: 将来の教育費のために貯めておくのがおすすめ。大学に行くときのお金や習い事の費用に使えます。
- 投資してみよう: NISAやジュニアNISAという制度を使って、子どものためにお金を増やすこともできます。
子どもにお金の大切さを教えよう
お金の使い方を子どもに教えるのも大切です。
パパ・ママくらいしか教えてくれる人は居ないですからね。
こんな方法はどうでしょう
- お買い物ごっこをする: 遊びながらお金の使い方を学べます。
- 家族で話し合う: 日常的にお金の話をすることで、子どもも自然とお金について考えるようになります。
将来の家計はどうなる?
教育費が減ることで、生活費や貯金に回せるお金が増えます。
どうしても避けられなかった教育費というものを軽減できるのはありがたいですね。
子育ての不安も少し減りそうですね。
幼児教育無償化は、みなさんの家計を助ける強い味方になります。この制度をうまく使って、子どもたちの未来をもっと明るくしていきましょう。お金の心配が減れば、子育ても楽しくなりますよ。